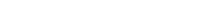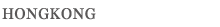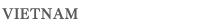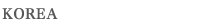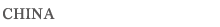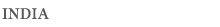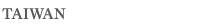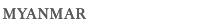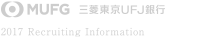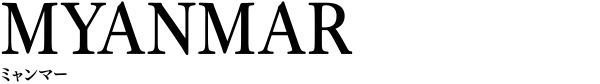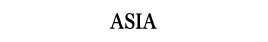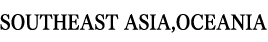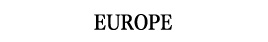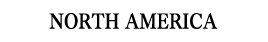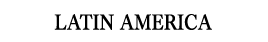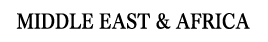首都 ネーピードー
言語 ミャンマー語
通貨 チャット
GDP 553億米ドル(2012年:IMF)
一人当たりGDP 868米ドル(2012年:IMF)
主要産業 農業
経済状況
(1)1962年に発足したネ・ウィン政権は、農業を除く主要産業の国有化等社会主義経済政策を推進してきたが、この閉鎖的経済政策等により、外貨準備の枯渇、生産の停滞、対外債務の累積等経済困難が増大し、1987年12月には、国連より後発開発途上国(LLDC)の認定を受けるに至った。
(2)1988年9月に国軍がクーデターにより軍事政権が成立し、社会主義政策を放棄する旨発表するとともに、外国投資法の制定等経済開放政策を推進したが、非現実的な為替レートや硬直的な経済構造等が発展の障害となり、外貨不足が顕著化した。2003年2月には、民間銀行利用者の預金取付騒ぎが発生し、民間銀行や一般企業が深刻な資金不足に見舞われた。更に、同年5月のアウン・サン・スー・チー氏の拘束を受け、米国が対ミャンマー経済制裁法を新たに制定したことが国内産業への打撃となり、経済の鈍化を招き、加えて、2004年10月には、EUがミャンマーの民主化状況に進展が見られないとして、ミャンマー国営企業への借款の禁止等を含む制裁措置の強化を決定した。2007年8月には、政府によるエネルギーの公定価格引き上げ(最大5倍)が翌9月の大規模なデモの発端となった。デモ参加者に対するミャンマー当局の実力行使を受けて、米・EUは経済制裁措置の強化を行い、豪州も金融制裁措置を取った。
(3)2010年11月に実施された総選挙で、連邦連帯開発党(USDP)が約8割の議席を確保、その直後に、アウン・サン・スー・チー氏の自宅軟禁を解除。翌2011年3月に、現テイン・セイン文民政権が発足し、民政移管が実現し、民主化を推進するとともに、経済改革等の取組を断行中である。例えば、中古車両の廃車許可(2011年12月から40年以上、翌2012年1月には生産から30年以上経過した車両)及びそれに代替する車両輸入許可を行うようになり、国内を走る車両が格段に新しくなった他、同年4月には、為替レート統一化に向け、管理変動相場制を導入した。また、同年11月には、外国投資受入の円滑化のため、制限的な内容だった外国投資法を改正した。
(4)欧米諸国は、ミャンマーが進めている政治・経済改革を評価し、米国は2012年11月に宝石一部品目を除くミャンマー製品の禁輸措置を解除し、EUも2013年4月に武器禁輸措置を除く対ミャンマー経済制裁を解除した。
(出典:外務省)
日系企業進出の目的・メリット
- ◯市場としての魅力。人口約65百万人を有するが、経済制裁などの影響もあり、外国企業の参入が未だ限定的。
- ◯9割を超える高い識字率に加えて、比較的廉価かつ豊富な労働力を有している。温和かつ真面目な国民性で、良好な治安・対日感情(親日的)。
- ◯豊富な天然資源(石油・天然ガス等)を有している。インド洋へ続く交通の要衝としての地理的優位性。
- (※2014年6月現在)
日系企業の進出動向
- ◯2014年6月末時点の日本商工会議所会員企業数は168社と、進出企業数は増加傾向(2010年12月末時点で50社、3年半で倍増)。進出の形態としては、未だ駐在員事務所が多い(ミャンマーの会社法上は支店扱い)。
- ◯電力・水道等のインフラが未整備であることから、製造業の進出は未だ進んでいない。
- ◯現在は縫製業を中心とした労働集約型産業が進出。今後、ティラワ経済特区の工業団地への進出が見込まれる。
現地における当行のステータス・強み
- ◯1995年の駐在員事務所開設後、米国の経済制裁を受けていた時代も変わらず、事務所を維持してきた業歴あり。2015年4月から支店開業(外国銀行では戦後初)。
- ◯円借款のエージェントバンクを務め、同国の発展に大きく寄与。
- ◯現地民間金融機関Co-operative Bankと業務提携。日本との米ドル決済ニーズに対応。IT化の進展により利便性が向上している。
上記内容については、信頼できると思われる各種データに基づき作成しておりますが、当行はその正確性・安全性を保証するものではありません。また、上記資料は情報提供のみを目的としたもので、当行の商品・サービスの勧誘やアドバイザリーフィーの受入れ等を目的としたものではありません。